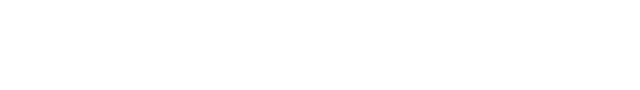寄生虫症 Parasitic diseases
寄生虫症の正確な診断、治療が可能な医療機関は多くはありません。たとえ大きな病院であっても、専門知識のある医師がいなければ病名が判明していても適切な治療を行うことができません。一方で、わざわざ大きな病院を受診する必要性も低く、診療所であっても適切な診断・治療さえできれば数日あるいは一日で完結することも可能です。自らの経験上、大学病院ですら年間数例程度の症例にもかかわらず、年間100例以上の寄生虫関連疾患を診療している施設は国内にはないと思われます(診療実績・下段の学術論文をご参照下さい)。
当院では以下の寄生虫症に関するご相談はお受けしております。しかしながら診療内容によっては保険適用にならない場合や明確に他疾患である場合も少なくはありません。主に行う検査は腸管寄生虫症に対する糞便検査や虫体鑑別などですが当院では実施できないものもありますので、寄生虫関連検査をご希望の場合は事前に実施可能なのかどうか確認するために必ずお電話で予約をお願いします(WEBからの予約はしないでください)。事前相談なく受診され検査ができないことによるトラブル事例が散見されますので何卒ご協力をお願いします。We accept consultations regarding parasitic diseases at our clinic. However, there are many cases where insurance does not cover the medical treatment, or where the treatment is clearly a different disease. The main tests we perform are fecal tests for intestinal parasitic diseases and ova identification, but some tests cannot be performed at our clinic, so if you would like to have a parasitic test, please make sure to make a reservation by phone or contact form by website in advance to confirm whether it is possible to perform the test (please do not make a reservation via the website). There have been many cases where patients have visited our clinic without prior consultation, which has resulted in trouble because the test cannot be performed. We ask for your cooperation.
特殊な寄生虫症で外注検査でも不可能な場合には研究所や大学研究室などに依頼することがありますが、あくまで医師の診察によって該当疾患を強く疑う場合のみで、感染の可能性がきわめて低いと判断した場合には検査のみのご要望にはお応えできないこともあります(これは専門診療科のある病院でも同様ですのでWEBからの予約はせずにまず事前にお電話でご相談下さい)。該当疾患が強く疑われ日本で未承認の治療薬が必要な場合は、臨床研究用として薬剤保管を行っている熱帯病治療薬研究班に属する医療機関をご紹介致します。
*プライマリケアにおける寄生虫症診療(医事新報社 日本医事新報【識者の眼】)
主な寄生虫症
- マラリア: 蚊(ハマダラカ)に刺されることによって感染します。流行地から帰国した後に突然の高熱で発症します。抗マラリア薬で治療します。当院では全ての抗マラリア薬を常備しています(感染症内科・マラリアの項目をご参照下さい)。
- アメーバ症: 病原体で汚染された水や食材、同性愛者の性行為などにより感染します。多くは腸アメーバ症で発熱、血便がみられますが、時に肝臓などに膿瘍(うみ)を作ることがあります(アメーバ性肝膿瘍)。メトロニダゾールで治療します。嚢子には効果が低いので嚢子駆除を行う場合にはパロモマイシンを使用します。
- ジアルジア症: 病原体で汚染された水や食材、同性愛者の性行為などにより感染します。渡航者下痢症で最も多い腸管寄生虫症です。メトロニダゾールで治療します。
- クリプトスポリジウム症: 病原体で汚染された水や食材などにより感染します。病原体は塩素で死滅しないので時に水道水からの集団感染事例もみられます。
- トリコモナス症: 感染症として問題となるのは膣トリコモナス症で性感染症の一つです。メトロニダゾールで治療します。
- トキソプラズマ症: ネコの糞便に含まれる病原体が感染源となります。妊婦が感染すると先天性トキソプラズマ症を起こすことがあります。健常人では多くは無症状ですが、免疫不全の場合には後天性トキソプラズマ症を起こすことがあります。
- トリパノソーマ症: ツェツェバエに刺されることによって感染するアフリカ睡眠病、サシガメに刺されることによって感染するシャーガス病があります。アフリカや中南米地域の風土病で外国人旅行者が罹患することはきわめて稀です。
- 蟯虫症: 盲腸に寄生する線虫で、肛門に産卵するので肛門周囲の強い掻痒感を自覚します。セロファンテープ法で虫卵を確認します。パモ酸ピランテルで治療します。
- 広東住血線虫症: 好酸球性髄膜炎の病原体で、感染幼虫を保有するナメクジ、アフリカマイマイの生食や接触により手などについた幼虫を摂取して感染します。治療薬はありません。
- 旋尾線虫症: ホタルイカの内臓に寄生していますので、刺身や生食で感染します。消化器症状のほか、幼虫が移行することによる皮膚症状(幼虫移行症)などもみられます。
- 糞線虫症: 日本では沖縄・奄美地方での発生がほとんどで、特に成人T細胞性白血病との重複感染が問題になります。イベルメクチンで治療します。
- 顎口虫症: ヒトへの感染は幼虫を保有する小型淡水魚や爬虫類の生食で感染します。ライギョやドジョウの踊り食いをした後に幼虫移行症として診断されることがあります。
- フィラリア症(糸状虫症): 蚊によって媒介されるリンパ系糸状虫(バンクロフト糸状虫・マレー糸状虫)、ブユ類によって媒介される回旋糸状虫症(オンコセルカ症)、アブ類によって媒介されるロア糸状虫(ロアロア)などがあります。虫種によってジエチルカルバマジン、イベルメクチンを選択します。
- 回虫症: ヒト回虫の場合は虫卵に汚染された野菜などを介して経口感染します。幼虫移行による肺炎(Loeffler症候群)、多数感染による腸閉塞などの症状もありますが、通常は無症状です。パモ酸ピランテルやアルベンダゾールで治療します。イヌ・ネコ回虫の場合はペットとの濃厚接触で感染することがあり、ヒトの体内では成虫になることができないので、幼虫が眼や中枢神経に移行して症状を起こします(トキソカラ症)。
- 鉤虫症: 幼虫の付着した野菜の摂取、土壌中の幼虫が手足の皮膚から直接侵入して感染します。ヒトに寄生するのはズビニ鉤虫、アメリカ鉤虫で成虫は小腸粘膜から吸血するために多数寄生すると貧血症状が現れます。幼虫移行による肺炎(Loeffler症候群)を起こすこともあります。パモ酸ピランテルで治療します。
- 住血吸虫症: 淡水産の巻貝に生息する幼虫(セルカリア)が水中でヒトの皮膚に直接侵入することで感染します。地域によって虫種が異なり、アジアでは日本住吸虫、メコン住血吸虫、アフリカや南米ではマンソン住血吸虫、アフリカや中東ではビルハルツ住血吸虫が分布しています。ビルハルツ住血吸虫は尿路系に寄生し、膀胱癌発症のリスクとなります。プラジカンテルで治療します。
- 横川吸虫症: 日本を含むアジア諸国に分布し、日本での感染機会はアユの生食が重要です。エジプトに分布する類縁の異形吸虫はボラなどの汽水産の魚類に寄生しています。健康診断の検便で最も多く検出される虫卵が本症といわれています。プラジカンテルで治療します。
- 肺吸虫症: 日本で本症の原因となるのはウェステルマン肺吸虫と宮崎肺吸虫で、淡水産のカニ(モクズカニ、サワガニ)の生食で感染します。主たる症状は呼吸器症状ですが、肺以外にも体内の各所に迷入することがあり、臓器特有の症状を示すことがあります。プラジカンテルで治療します。
- 肝吸虫症: アジア地域に分布し、コイ科の淡水魚の生食で感染します。東南アジア地域では別種のタイ肝吸虫が分布しています。胆管内に寄生するので経過とともに肝機能異常、肝硬変、胆管細胞癌などを起こすことがあります。プラジカンテルで治療します。
- 条虫症: いわゆるサナダムシです。日本海裂頭条虫はサケやマスの筋肉内に幼虫が寄生しているので、刺身をよく食べる日本人にはよくみられる寄生虫症です。他に牛肉の生食で感染する無鉤条虫、豚肉の生食で感染する有鉤条虫も輸入例として散見されます。多くは無症状ですので、虫体の一部(片節)が切れて便に混じって排泄されることで感染に気が付きます。プラジカンテルで治療します。但し有鉤条虫は、幼虫が虫卵から出て身体の各部に運ばれて有鉤嚢虫を形成することがあるために慎重な対応が必要となります。特に脳有鉤嚢虫症は脳膿瘍と疑われることがあります。
- 包虫症(エキノコックス症): 日本では北海道に分布する多包条虫がよく知られていますが、世界の牧羊地帯には単包条虫が分布しています。ヒトへの感染はキツネやイヌの小腸に寄生する成虫が排泄した虫卵を偶然摂取することで成立します。10年以上無症状であることが多く、肝機能異常や肝腫大で発見され、他臓器への転移もみられることがあります。早期診断による肝切除が根本的な治療になります。エキノコックス抗体検査は北海道衛生研究所に依頼します。
- 当院ではアニサキス症の内視鏡による摘出はできません。
サナダムシの治療について
サナダムシ(条虫)は国内で最もよくみられる寄生虫症の一つで、特に日本海裂頭条虫はサケやマスの生食で感染することから、刺身をよく食べる日本人に特徴的な寄生虫症とも言えます。多くは感染しても無症状で、感染の機会から数か月程度経過して体長数メートルになった段階で虫体の一部(片節)が切れて便と共に排泄されますので、患者さんはこの時に便に白い物体が混じっていたと気が付き、慌てて病院を受診して感染が判明します。日本海裂頭条虫では片節は薄く動きませんが、無鉤条虫の場合は片節に厚みがあり、排泄されても動いていることからさらに驚いてしまうでしょう。虫体を持参しても日常的に診られるものではないので、大きな病院(おそらく消化器内科)を紹介されることになると思われますが、消化器内科は寄生虫の専門ではなく、適切な治療法がわからずに異なった薬が処方されたり、治療までに時間を要することもあるようです。治療はプラジカンテル(ビルトリシド®)という錠剤を1回内服すれば終了です。内服後、頭部が腸管に付着していた虫体がそのままの形状で排泄されます。確実に駆虫されたかどうかはこの頭部を確認する必要がありますが、鉛筆の芯程の頭部を見つけるのは容易なことではなく、万が一確認できなくても1か月程度してから検便による虫卵検査を行い、虫卵が検出されなければ根治となります。当院ではプラジカンテルを常備しておりますので、虫種を鑑別後に1日で治療終了します(保険適用ではありません)。
<日本海裂頭条虫の成虫>
▲中央やや上部に見える細い糸ような先端が頭部です
排便時に寄生虫?が出たという方へ
当院にはこのような方が連日受診されていますが、診察は以下のような流れとなります。
- 排泄された寄生虫らしきもの(寄生虫とは限りません)を採取して容器などに入れてご持参ください。視診である程度は判別がつきますが、治療は虫体鑑別検査後となります。
- 直接ご持参できない場合はスマートフォンなどで写真をお撮りいただき、診察時にお見せください。但しスケールが不明確ですので判別は困難です。
- 虫体がない場合は糞便検査を行いますので、当日お渡しする採便容器に検体を採取していただき後日お持ちいただくことになります。
- 寄生虫がいるかもしれないなど、ご相談のみの場合は自費診療となりますのでご了承ください。
- 他の病院で「コンバントリン」という薬が処方された場合、これは主に蟯虫症の治療薬で条虫症には無効です。
*皮膚を虫が這う・皮下に虫がいると自覚される方へ 对于那些感觉皮肤上有昆虫爬行或皮肤下有昆虫的人 Dành cho những người cảm thấy côn trùng bò trên da hoặc có côn trùng dưới da
開発途上国での滞在歴や淡水魚の生食など、特殊な曝露歴がなければ腸管寄生虫症でそのような自覚症状が出ることはほとんどありません。該当する場合は皮膚寄生虫妄想や他疾患の可能性があります。皮膚の症状がある方はまず皮膚科をご受診ください。他の医療機関で寄生虫症の可能性がないと言われた場合で当院を受診される場合には、行った検査内容を精査する必要がありますので診療情報提供書(紹介状)をご持参ください。 ご理解いただけない方によるトラブルが散見ますのでご持参のない場合は診療をお断りすることがあります。
Unless you have a history of special exposure, such as a history of staying in a developing country or eating raw freshwater fish, intestinal parasitic infections rarely cause such symptoms. If this is the case, it may be delusional skin parasitosis or another disease. If you have skin symptoms, please first visit a dermatologist. If you have been told by another medical institution that there is no possibility of parasitic infection and you visit our clinic, please bring a medical information report (referral letter) with you, as we will need to thoroughly examine the results of the tests that have been performed. We have seen occasional problems caused by people who do not understand this, so we may refuse to treat you if you do not bring this with you.
除非您有特殊接触史,例如居住在发展中国家或食用生淡水鱼,否则肠道寄生虫感染很少会引起此类症状。如果出现这种情况,则可能是妄想性皮肤寄生虫病或其他疾病。如果您有任何皮肤症状,请先去看皮肤科医生。如果您被其他医疗机构告知没有寄生虫病的可能性并来本院就诊,请携带您的医疗信息表(介绍信),因为我们需要仔细检查您的检查结果。我们偶尔会看到一些不理解的人造成的问题,因此如果您没有携带必要的文件,我们可能会拒绝治疗。
Trừ khi bạn có tiền sử tiếp xúc đặc biệt, chẳng hạn như ở một quốc gia đang phát triển hoặc ăn cá nước ngọt sống, nhiễm ký sinh trùng đường ruột hiếm khi gây ra các triệu chứng như vậy. Nếu đúng như vậy thì có thể đây là trường hợp mắc bệnh ký sinh trùng da ảo giác hoặc một căn bệnh khác. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào về da, hãy đến gặp bác sĩ da liễu trước. Nếu một cơ sở y tế khác thông báo với bạn rằng không có khả năng bạn mắc bệnh ký sinh trùng và bạn đến bệnh viện của chúng tôi, vui lòng mang theo tờ thông tin y tế (thư giới thiệu) vì chúng tôi sẽ cần kiểm tra cẩn thận kết quả xét nghiệm mà bạn đã thực hiện. Chúng tôi đã thấy một số vấn đề thỉnh thoảng xảy ra do người dân không hiểu biết, vì vậy chúng tôi có thể từ chối điều trị nếu bạn không mang theo các giấy tờ cần thiết.
▲典型的な幼虫移行症(皮膚這行症):このような所見がみられる場合には詳細な問診のうえ血液検査を行うことがありますが、上記のような内容の場合は当院では検査は行いませんのであらかじめご了承下さい。
当院における寄生虫診療の現状(日本臨床寄生虫学会誌 2020年版に掲載)
日本国内の臨床分野における寄生虫症例はそう多くはないが、その中でも比較的遭遇する可能性が高い条虫症の場合、知識があれば糞便検査を行い虫卵が見つかれば虫種を確認のうえ治療を完結することはそれほど困難なことではないだろう。しかしながら、条虫症だけではなく寄生虫症を的確に診断、治療できる臨床医は多くはない印象である。一方、専門医を擁する大学病院や総合病院では原則的に情報提供書を必要とすることから、患者から直接アクセスすることが困難なこともあり、感染症を専門とする部署であっても年間症例数が極端に多い訳ではない。さらに寄生虫症の多くは届出感染症ではないことからその実態は不明確である。当院は専門診療を行っているものの情報提供書などは不要であり、寄生虫症に関してホームページ上で多くの情報提供を行っていることからか、ほぼ関東全域から寄生虫関連を主訴とする患者が連日訪れている。日常の診療において虫体様物体の排泄を経験する患者や、全く違った薬剤が処方されて駆虫に失敗している患者、ならびに自身で寄生虫症を疑う患者が予想以上に多いことを実感していることから、プライマリケアにおける寄生虫診療の現状を報告し、その課題について考察する。
当院は東京都千代田区に所在し、感染症内科および渡航医療を専門とする無床診療所である。2019年6月の開院より2020年5月までの1年間に受診した患者1315名の中で感染症内科を希望して受診した患者368名のうち、主訴が寄生虫関連で受診した患者184名(男性:76名、女性108名)を対象として解析を行った。
平均年齢は37.8±15.0歳、主訴は虫体排泄が74名で最も多く、次いで寄生虫相談が35名、寄生虫検査希望が22名であった。虫体排泄を主訴に受診した患者の多くは排泄物の現物または写真撮影を行い持参していた。このほとんどは糞便検査を行い、虫卵および虫体の有無を確認した。確定診断に至った例は33例で、日本海裂頭条虫25例、無鉤条虫7例、アニサキス1例であった。アニサキスは口腔内から検出された虫体を患者自身が持参し、病理検査に提出して判明した。寄生虫相談の主な内容は広東住血線虫5例(内容:カタツムリに接触、食べ物に入っていたので心配、検査・治療をして欲しい)、住血吸虫4例(内容:アフリカに滞在して淡水を浴びてしまったので検査・治療をして欲しい)、幼虫移行症3例(内容:皮下に虫が這っているので検査・治療をして欲しい、脳に幼虫が入り込むと聞いたので心配)、顎口虫(内容:皮下に虫がいるので調べたらこの病気が見つかったので心配)、トキソカラ(内容:イヌを飼っていて回虫が見つかったので検査・治療をして欲しい)が各1例であった。希望された寄生虫検査の内容はトキソカラ4例、肺吸虫4例、トキソプラズマ3例、肝蛭2例、ランブル鞭毛虫、顎口虫、エキノコックスが各1例であった。実際に寄生虫症を疑い検査で判明した病名は、熱帯熱マラリア1例、ジアルジア症2例、腸アメーバ症2例、異形吸虫症1例、回虫症1例であった。その他の受診者では「体の中に虫がいる」、「皮膚に虫が這っている」などを訴えて来院する患者が複数みられ、渡航歴や食歴など詳細な問診および検査を行い寄生虫症の可能性がほとんどないことを説明しているにもかかわらず納得されない、いわゆる「寄生虫妄想」と考えられる患者も散見された。この患者の多くはこれまでに大学病院を含め多くの医療機関を受診しており、いずれでも同様の説明を受けているにもかかわらず受診している傾向がみられた。
今回経験した寄生虫症の中で最も多かったのは日本海裂頭条虫症であったが、国立感染症研究所寄生動物部の報告によれば、2007年から2017年の間に確定診断した裂頭条虫症例は114例と学術誌の症例報告数を加えた439例であり、年平均では40例前後と推定されている。また1990年から2017年までの間に確定したテニア(無鉤条虫・有鉤条虫・アジア条虫のいずれか)症例は88例と文献検索による95例を合わせて183例であり、年平均では6~7例と推定されている1)。寄生虫症診療を担うのは多くが感染症科を有する医療療機関であると推測され、近隣医療機関からの紹介患者が多くを占めると考えられるが、今回の解析で想像している以上に寄生虫症を疑い身近な医療機関を受診する患者が多い印象を受けた。しかも条虫症に関しては国内で年間に発生する症例の多くを一医療機関、且つプライマリケアの領域で経験したことになった。寄生虫症は身近な健康問題として起こり得るにもかかわらず、患者はどの医療機関を受診してよいかわからないことが多い。またプライマリケアを担う医師も診療経験が少ないことから、適切な診断や治療がなされていないことも実感した。特に条虫症に関しては、特に説明なく回虫などの駆虫薬としては有名だが条虫には無効なパモ酸ピランテルが処方され、虫体排泄が持続している患者も複数確認された。多くの寄生虫症は適切な診断がなされれば抗寄生虫薬により短期間での治療が可能である。当院では国内で承認されているほぼ全ての抗寄生虫薬を常備しており、今後も寄生虫感染を不安に思われる患者に対して正確な情報の提供、適切な治療が行える医療体制を維持していきたい。
<文献>
1)山﨑 浩 他(2017):わが国における条虫症の発生状況.国立感染症研究所IASR Vol. 38 p.74-76: 2017年4月号https://www.niid.go.jp/niid/ja/allarticles/surveillance/2406-iasr/related-articles/related-articles-446/7213-446r04.html.